
豊後大野市三重町の内山に、蓮城寺というお寺があります。
通称内山観音と呼ばれていて、観音堂には千手観音、薬師堂には薬師如来と千体薬師が安置され、敷地内には延命地蔵や子育て地蔵も祀られています。
向かいには内山公園があり、春は桜、秋は紅葉が美しく、夏は木陰や小川のせせらぎで涼をとるなど、地元民の憩いの場としても親しまれています。
県外からも参拝者が訪れる名所ですが、観光地のにぎわいはなく静かなたたずまいです。
この記事では、内山観音の由来、お守りと御朱印、般若姫伝説と伝説にまつわる見どころについてご紹介していきます。
内山観音(蓮乗寺)はどこにある?
三重町から、佐伯市宇目や宮崎県延岡へ続く国道326号の途中、左の脇道に入り1Kmほど進んだ場所にあります。JR豊肥本線三重町駅からですと、車でおよそ8分で到着します。
| 所在地 | 大分県豊後大野市三重町内山527 |
| 電話番号 | 0974-22-0598 |
| 駐車場 | 約80台(隣接の内山公園駐車場含む) |
内山観音(蓮城寺)の由来

蓮城寺は、真名野長者(まなのちょうじゃ:炭焼小五郎)が欽明15年(554年)に建立(こんりゅう)した県内で最も古いといわれるお寺です。
貧しい炭焼き青年だった小五郎は、都からきた玉津姫との出会いによって真名野長者と呼ばれるほどの富を得ました。
長者は仏教への信仰が厚く、唐(中国)の天台山に黄金3万両を贈ります。天台山はそのお礼として、連城法師に薬師観音の尊像を持たせて長者の下へ遣わしました。
この尊像をまつるために建立されたのが蓮城寺です。
また、内山という地名は、真名野長者の娘般若姫の婿であった橘豊日皇子(たちばなとよひ:後の用明天皇・聖徳太子の父)が、身重の姫を置いて一足先に都に戻る際に「我が子を此処に置く。今よりはこの里を大内山と名づくべし」とお書きになったことに由来するといわれています。
お守り・御朱印
お守りと御朱印は内山観音寺務所で入手できます。呼び出しボタンを押すと対応していただけるようです。
私がうかがった時は、コロナ感染防止対策への配慮から「参拝の自粛をお願いします」との張り紙があったので、いつでも行ける地元民としてはお声掛けをひかえさせていただきました。
お守りや御朱印をご希望の方は、事前に電話でお問い合わせいただくと確実ですね。
【お問い合わせ】蓮乗寺:0974-22-0598
般若姫伝説

般若姫は真名野長者夫妻の一人娘で、誕生には諸説があります。
蓮乗寺では、子宝に恵まれなかった真名野長者夫妻が、百済(くだら:今の朝鮮)の貿易商竜伯が持参した一寸八分観音を信仰したことで授かったとされています。
月の精を宿すといわれ「美しくも短命である」というお告げのもと誕生。成長した姫の美しさは、遠い都や異国の唐の国まで知れ渡るほどでした。
噂はやがて欽明天皇の耳にも届き、「般若姫を橘豊日の后に迎えたい」と真名野長者のもとへ使者を遣わせました。しかし、姫を愛する長者夫妻は大事な一人娘を手放そうとしません。
豊日皇子も般若姫を諦めることができず、身分を隠して自ら豊後の国に下ります。
途中、三輪明神や山王権現の加護を受けながら長者のもとへたどり着き、牛飼いとして働き始めました。
ある時、般若姫は病に倒れます。
「姫の病を治すには”笠掛けの的”を射よ」というご神託を賜りますが、だれも何のことかわかりません。牛飼いに身を隠している皇子だけが”笠掛けの的”を用意し、見事に”的を射る”ことができました。
※”笠掛けの的”とは、今でいう流鏑馬(やぶさめ)のことで、この時から始まった神事といわれています。
病が治った般若姫は皇子と結婚し、三重の地で幸せに暮らしていました。
ところが、皇子を探し続けていた都の使者が迎えに訪れ、皇子は都へ戻らなければならなくなりました。般若姫はこの時お腹に赤ちゃんがいたので一緒に行くことができません。
そこで皇子は「生まれた子供が男の子ならその子と一緒に上洛してください。女の子なら長者の跡継ぎにしてあなただけ上洛してください」と言い残して一人都に戻っていきました。
やがて般若姫は無事に女の子を出産。皇子との約束を果すため、娘を残し一人で上洛します。
そのお供は総勢1000余人。臼杵港から出航した船は、大小合わせて120隻の大所帯だったといわれています。
道中、般若姫一行は不運にも2度の暴風にみまわれます。
多くの家人を亡くした姫の悲しみはことのほか深く、「この上自分の幸せなど、どうして考えられようか」と海に身を投げてしまわれます。
すぐに泳ぎの達者な船乗りによって救助されたものの、姫は生きる気力を完全になくしておりました。日に日に弱り、数日ののちに帰らぬ人となったのです。
お告げのとおり、19年の短い生涯を閉じたのでした。
千日参りとは?
千日参りは、年に一度一寸八分観音が開帳される日にお参りすることをいいます。「この日にお参りをすると千日分のご利益がある」といわれることから、このように呼ばれるようになりました。
一寸八分観音は般若姫の守り本尊で、毎年1月10日にだけお目にかかることができます。
安産や海難予防の仏さまとして厚く信仰され、日ごろは静かなお寺も、この日ばかりは多くの参拝者が訪れて賑わいます。
内山観音の見どころ
それでは、内山観音をご一緒に観てまいりましょう。

蓮乗寺の門をくぐると正面に大師堂があります。

ちょっとわかりづらいですが、大師堂の左側に一寸八分観音への参道があります。入り口をくぐって進み、橋を渡った先にお堂が見えてきます。橋の上から見下ろすせせらぎは情緒があり、お堂を目前にしばし見入ってしまいました。

こちらが、秘仏一寸八分観音を祀る長者堂です。
観音様のご利益で子宝を授かった真名野長者の妻玉津姫は、この観音様を上洛する娘般若姫に贈りました。
船で都へ向かう途中遭難した般若姫は、一寸八分観音を海に投じたことで難を逃れたといわれています。後に大魚のお腹から発見された観音様は、聖徳太子の命によって蓮乗寺に差し戻されて今日に至ると伝えられています。

大師堂まで戻り、右手の階段を上がり本堂へ向かいます。趣のある竜の手水鉢で手を洗い清めます。きれいなタオルがかけられていて、お寺の方のお心遣いが感じられました。

こちらがご本尊の千手観音をお祀りしている本堂です。

本堂でお参りを済ませ左手方向に進むと、合格祈願の聖徳太子のお堂があります。受験前にお参りをして、桜の季節にお礼参りに来られる学生さんも多いようです。

聖徳太子堂の右斜め向かいあるのが延命地蔵です。こちらで健康長寿を祈願できます。

延命地蔵の右手には子育て地蔵と子安地蔵(こやすじぞう)が祀られています。安産や子供の成長を祈ったり、水子の供養にも参拝者が訪れます。

子育て地蔵をから道路にでて左手に進み、薬師堂に向かいます。途中、右側に真名野長者伝説にまつわる金亀が渕を見ることができます。
真名野長者伝説についてご存じない方は気になるかもしれませんね。あとで簡単にご紹介させていただきますので、興味のある方はご一読いただければと思います。

薬師堂が見えてきました。室町時代に製作されたといわれる千体薬師像は、実際は998体という説もありますが、こちらの案内板には1008体と書かれています。

出入口両側には仁王様がおられ、かなりの迫力です。

こちらがご本尊の薬師如来と木彫の千体薬師像です。
大分県の重要文化財にも指定されている薬師像は、背丈がおよそ65cmで蓮華座に立たれています。左手に宝珠を持ち、右手は人々の怖れをのけて保護と至福を与える施無畏(せむい)の印を結んでおられます。背格好は同じですが、よく見るとひとりひとり異なるお顔立ちをされておりました。

薬師堂から道路を下るとその先左側に、般若姫の巨像へ行く道があります。
入り口付近には鳥居や県指定有形文化財があり、姫のもとへ続く小道には石の仏さまが道案内のように点々とおられます。

こちらが般若姫像です。左右に長者夫妻の像も設置されています。
日ごろ山あいにポツンと浮かび上がる姫の姿がなんとなく寂し気に感じていたので、ご両親がそばにおられるのを見てほっとした気持ちになりました。
生い茂ったススキがうら悲しい雰囲気でしたが、澄みきった青空を背景にした般若姫のお顔は凛と美しかったです。

蓮乗寺の駐車場の奥にある内山公園です。
赤い橋げたの下に見えるなだらかな桜並木は、花が咲き誇ると見事な景観で、毎年花見客を楽しませてくれます。
3週間あまり過ぎて、桜が咲きました!あいにくの曇り空ですが、ご覧の通り見事に咲き誇っています。


公園内には広場やステージ、真名野長者と般若姫物語にまつわる建造物があります。この建物の奥には伝説の絵巻物が展示されています。
真名野長者伝説
真名野長者伝説についてご存じない方もおられるかもしれません。簡単に般若姫のご両親、真名野長者夫妻の馴れ初めや金亀が淵にまつわるお話をご紹介しますね。
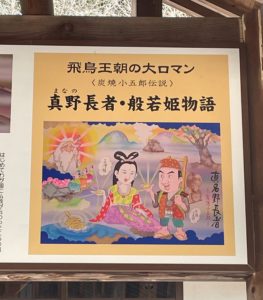
欽明天皇の時代、豊後の国(大分)の三重町玉田というところに炭焼小五郎と呼ばれる若者がおりました。
同じころ、大和の都に玉津姫という年頃の姫がいて、顔一面の痣(あざ)にとても悩んでおられました。「なんとかこの痣を治したい」と三輪神社で亥の刻参りをしたところ、満願の日に夢のお告げがあります。
『豊後の国、三重の里山に住む炭焼小五郎と夫婦になれば、ゆくゆくは長者になるだろう』
お告げを信じた玉津姫は、16歳になった翌春に豊後に下りました。
三重までもうすぐというところで夜になり、途方に暮れていたところ白髪の老人が現れます。
「明日、炭焼小五郎に会わせてあげるから今夜は泊まっていきなさい」
老人の好意に甘え、眠りについた玉津姫にふたたび夢のお告げがあります。
『金亀が渕で顔を洗えば痣が落ちる』
翌朝、みすぼらしい小屋に玉津姫を案内した老人はそのまま消えてしまいます。
やがて、粗末な服を着て、全身が炭で真っ黒に汚れた炭焼小五郎が帰ってきました。
姫が三輪明神のお告げで訪ねてきたことを伝えると、小五郎は「自分一人が食べていくのがやっとの生活なので、とても夫婦になることはできない」と断ります。
しかし、姫の決意は固く二人は一緒に住むようになりました。
玉津姫は都から持ってきた黄金を小五郎に渡し、「これで食べ物を買ってきてください」と頼みます。いわれるがまま出かけた小五郎は、ほどなく手ぶらで帰ってきます。
「食べ物はどうしたのですか?」と尋ねる姫に、小五郎は「下の淵にカモがいたので、あなたにいただいた石を投げて捕まえようとしたのですが当たりませんでした」と答えます。
姫は「なんとまぁ!あれはただの石ではありません。黄金という宝物なのですよ」と教えます。
「あのような石なら炭焼窯(すみやきがま)の周りや下の淵にたくさんありますよ」という小五郎の言葉に驚いた姫は、その場所に連れて行ってもらいました。
小五郎の言うとおり淵にはたくさんの黄金があり、やがて黄金の亀も浮かび上がってきたのです。
「ここが夢のお告げの金亀が渕にちがいないわ!」
そう思った玉津姫が淵の水で顔を洗ったところ、ずっと悩んでいた痣がみるみる消え美しい姫となりました。姫のすすめで全身を淵の水で洗った小五郎も美男になりました。
二人は黄金を拾い集めてたちまち大金持ちになり、真名野長者と呼ばれるようになったのでした。
まとめ
内山観音についてご紹介しました。
内山は、遠足やお祭り、真名野長者(炭焼小五郎)伝説にちなみ、地元民にとっては子どもの頃からなじみのある場所です。
私は穏やかで優しい雰囲気を感じる内山が大好きで、大人になってからも、心がすり減ったり疲れ切ってしまった時にふらりと出かけては癒された経験が何度となくあります。
ですが、内山観音のことを知りたい!と思って訪れたのは今回が初めてでした。
由来を知って、伝説の人物に思いをはせながらゆっくりと見て歩くおもしろさに、時間が経つのを忘れてしまいました。
まるで日本昔ばなしに出てくるような風景の中にあって見どころ満載。静かに散策するもよし、お子様と自然に親しみながらのんびり過ごすのもよし。
四季折々の情緒をたのしめる内山の地に、ぜひ、足をお運びいただければと思います。
